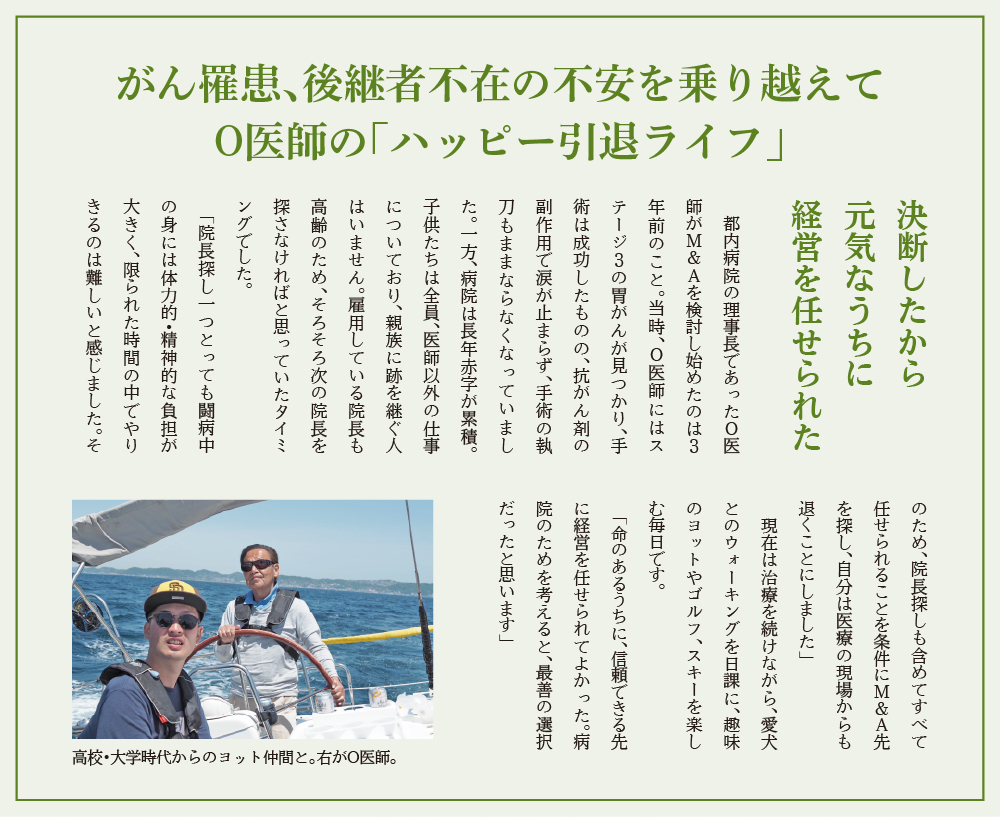幸せなM&Aは
“引退後の生活”で決まる
クリニックの事業承継をスムーズに行うには、引退後の生活をイメージすることも大切です。医療機関M&Aの専門家が、幸せな引退後のポイントについて解説します。
仕事を続けるかきっぱりやめるか
医療機関の事業承継を行っても、院長先生や理事長先生が必ずしも自分のクリニックを離れなければならないわけではありません。医療と経営の両方の責任を一手に引き受けていた院長先生・理事長先生が、融資の個人保証が外れ、資金繰りや人材確保のために奔走することがなくなって、医師としての仕事に専念できるようになることも、M&Aによる事業承継における「引退」の一つの形です。一方、承継後は医師の仕事はきっぱりとやめ、趣味など、これまでやりたいと思っていながら忙しくてできなかったことを実現してゆく。M&Aでは、このような一般的にイメージされる「引退」を選ぶことも可能です。どちらを選ぶにしても、院長先生・理事長先生がまずは「引退」についての理想のイメージを持ち、自分の意思をはっきりと固めること。これが、事業承継先選びや条件、ひいては事業承継が成功するかどうかに大きく関わってきます。仕事を続けるにしてもやめるにしても、院長先生・理事長先生が希望する引退ライフを送れることが、クリニックの経営改善と同じぐらい大切なのです。
引退後の生活から見たM&Aのメリット
医師と経営者という二足の草鞋を脱ぐ方法、つまり出口戦略には事業承継と解散(廃業)があり、事業承継には親族内承継、親族外承継、M&Aがあります。引退後の生活を考えた時、M&Aには他の方法と比べて次のようなメリットがあります。
① お金
M&Aの場合はクリニックの営業権に対して対価が支払われるため、利益が出ているクリニックの場合は院長先生・理事長先生に一定の譲渡益(収入)が発生します。医師に退職金はありませんが、譲渡益が退職金代わりになり、引退後の生活を支え、趣味や旅行などに使うこともできます。借入金や経営状態などにより譲渡価値がないとみなされる場合でも、金融機関からの融資の個人保証を外すことにより、将来の返済負担をゼロにすることが可能です。
② 家族
親族内承継の場合、例えば子供に税金の負担をかけまいと、自己判断で不要な保険に加入したり借金をしてかえって後継者である子供を苦しめ、引退後、家族間に問題を抱えるケースもあります。M&Aの場合は専門知識のある第三者に譲渡するのでこうしたトラブルを回避することができます。
③ メンタル
診療記録の法定保存期間が5年間あるため、閉院した場合は自宅に大量のカルテを保管しておかなければならず、患者様から相談があったらいつでもカルテを出さなければならないなど、閉院したクリニックの責任や業務が引退後もしばらくはついて回ります。また、親族内承継、親族外承継の場合は、個人的な関係がなくならない以上、譲渡後も相談を受けるなど、何かしらの関与は避けられません。M&Aで経営や人事などを信頼してまかせられる第三者に譲渡できた場合は、院長先生・理事長先生はクリニックへのすべての責任を手放し、安心して引退後の生活を楽しむことができます。
パートナーの選定も重要
クリニックのM&Aを行う場合は、譲渡先の紹介をM&A仲介会社に依頼することになります。医療機関の譲渡対価は一般企業とは異なる基準で算出されるため、医療機関専門のM&A仲介会社や、医療機関を多く扱う仲介会社に相談する方がよいでしょう。譲渡対価の算定は仲介会社によって異なり、また、手数料の金額や方式にも注意が必要です。特に借入金のあるクリニックの場合は、借入金も含めて移動資産とみなして手数料を算出する方式かどうかで、手残りが大きく異なります。院長先生・理事長先生の悩みや引退後生活についての希望を理解し、寄り添ってくれる仲介会社であることも大切です。
まとめ
後継者問題はクリニックにとって大きな課題であり、後継者不在の場合は閉院や解散か、M&Aかで悩まれている院長先生・理事長先生もいらっしゃることでしょう。多くの選択肢がある中で、地域医療や患者様のためにはどの方法がよいのかを検討することはもちろんですが、院長先生・理事長先生自身の引退後の生活をイメージしたときに、最も悔いがなくハッピーな方法を選択するという視点もあわせて持つことが大切です。