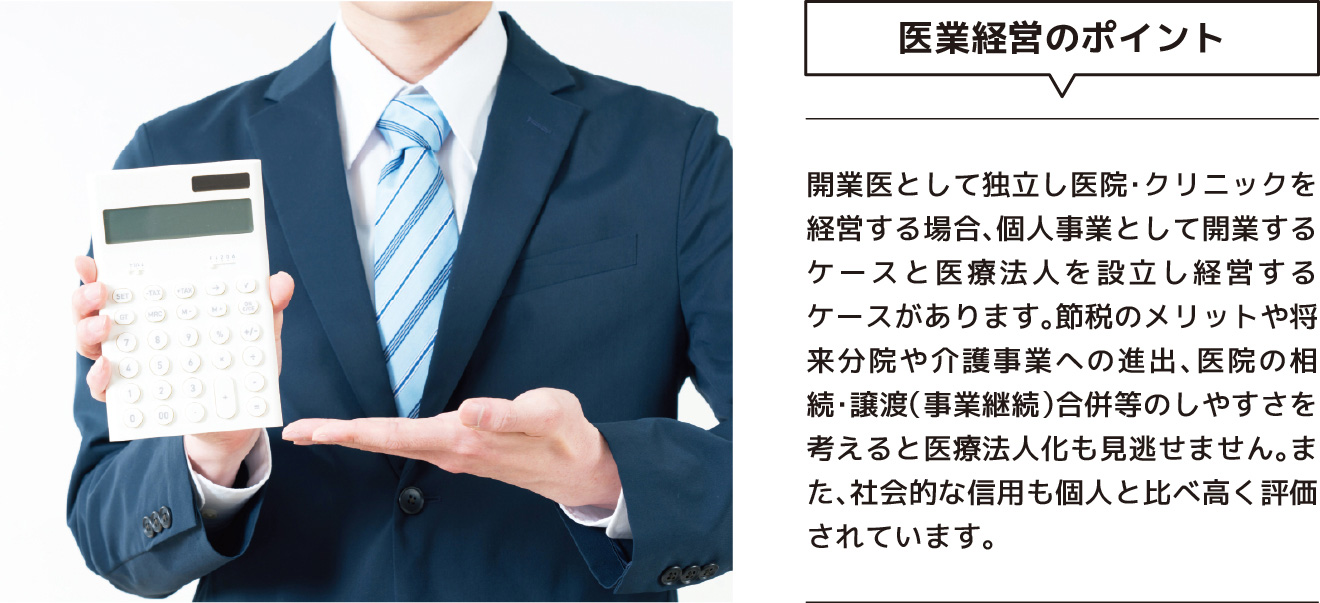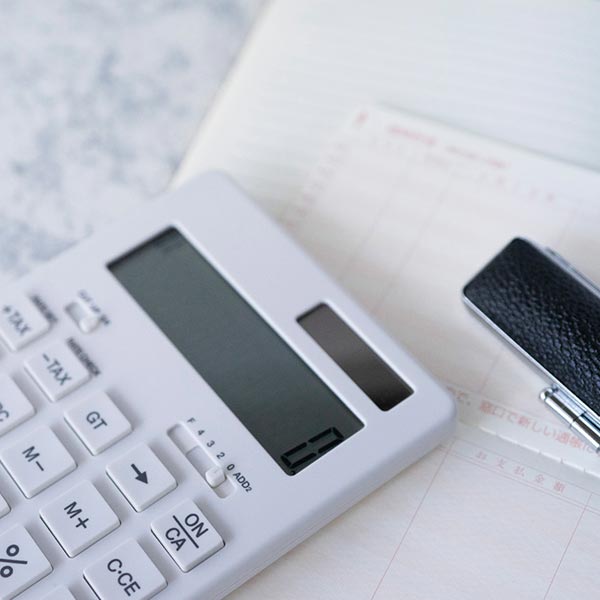第1回 医療機関の税務相談
– 節税対策編 –
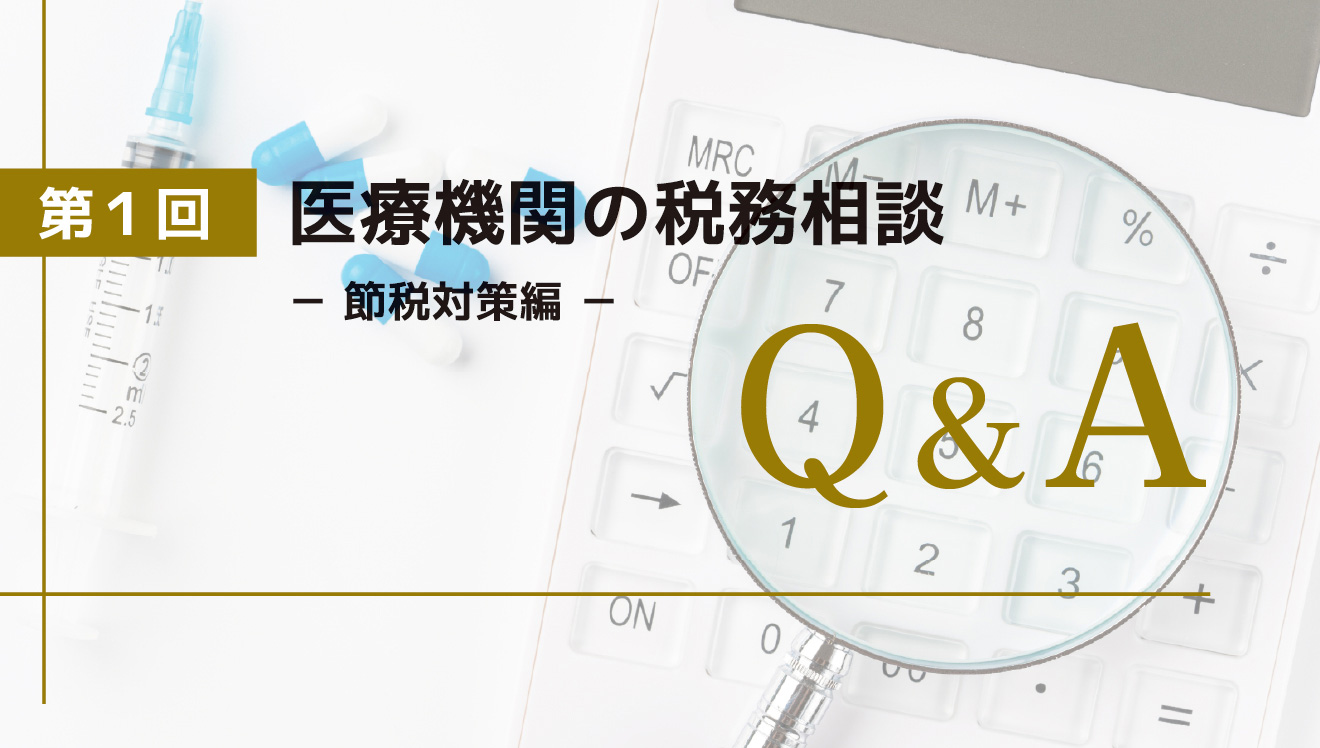
Q 個人事業と医療法人の違いについて教えてください。
A 開業医として独立し医院・クリニックを経営する場合、個人事業として開業するケースと医療法人を設立し経営するケースがあります。個人事業の場合、これまで築き上げた財産は院長(医師)個人のものです。医療法人が将来解散や廃業した場合、国、地方公共団体、または一定の医療法人のものとなってしまいます(第5次医療法改正により平成19年4月1日以降設立された医療法人の場合、定款で定められた場合は出資額まで返還)。また、大きな違いのひとつとして個人事業の決算期は12月で事業所得として確定申告を行ないますが、医療法人の決算期は定款に定めることによって自由に設定でき、法人から給与が支払われます。
法人化のタイミング
個人事業から医療法人化への見極めは、節税だけでなく将来性やメリット・デメリットも熟考した上で判断しましょう。顧問税理士からのアドバイスや具体的な数字を算出した比較検討も必要不可欠です。例えば、所得税率が33%に達したり、社会保険診療報酬が5,000万円を超え、概算経費率が使えなくなった頃がひとつの目安になります。
医療法人のメリット・デメリット
多くの時間と労力と資金をかけて医療法人を設立するには、それに見合うだけのメリットがあるからです。しかし、デメリットやリスクがない訳ではありませんので、慎重かつ総合的な判断が必要になります。
【メリット】
- 院長(理事長)や法人に従事している院長の家族(従業員)に法人から給与を支払うため、所得を分散する事が可能で税金の負担を軽減できる。
- 給与の支払いを受けている院長(理事長)や院長の家族(従業員)に退職金の支払いができる。
- 分院や介護事業等の新規事業展開、吸収合併、事業承継ができる。
- 院長(理事長)がなくなっても法人は継続できるので、新たな院長(理事長)を選出するだけで事業を継続できる。
- 収支を個人と法人で明確に区分できる。
- 銀行等の金融機関や患者等、対外的な信用力が高まる。
【デメリット】
- 法人の利益を院長(理事長)が自由に使う事ができない。
- 役員賞与や余剰金の配当はできない。
- 社会保険への強制加入が義務付けられている。
- 決算期ごとに、財産目録、決算書に加え、事業報告書の作成が義務付けられる。
- 交際費は経費として認められる額に制限がある。
- 理事を3名以上、監事を1名以上確保する必要がある。
Q 所得税の節税対策に良い方法がありますか?
A 勤務医の頃は給与から自動的に所得税や住民税が天引きされていたと思います。しかし開業医になると、自分で税金の納付や申告をする他にも、スタッフの給与から税金を徴収して納付・申告も行なわなければなりません。そのため開業医でもできる節税対策が必要になります。
【青色申告は効果的な節税対策】
効果的な節税対策に、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという青色申告制度があります。青色申告には次のような様々な特典がありますが1年間に生じた所得を正しく計算し申告するための収入や必要経費の取引状況を記帳し、その書類を保存しておく必要があります。
【青色申告の特典】
1 青色申告特別控除
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出している場合には、最高65万円を控除する事ができます。
2 青色事業専従者給与
青色申告者と家族(生計を一にする配偶者とその他の親族)のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専従している人に支払った給料・賞与は、届出書に記載された金額の範囲内で適正な金額であれば、必要経費として認められます。
3 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年にわたって各年分の所得から差し引く事ができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受ける事も出来ます。